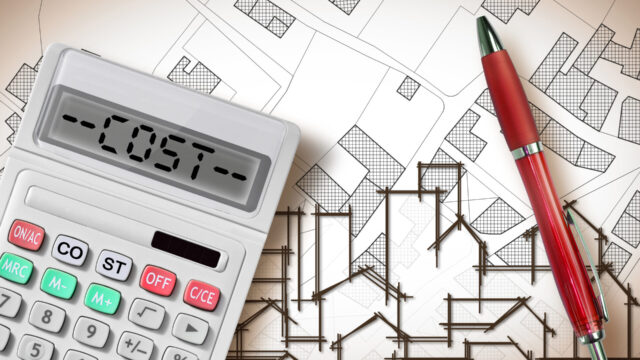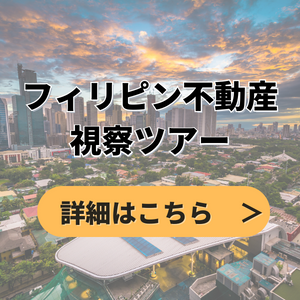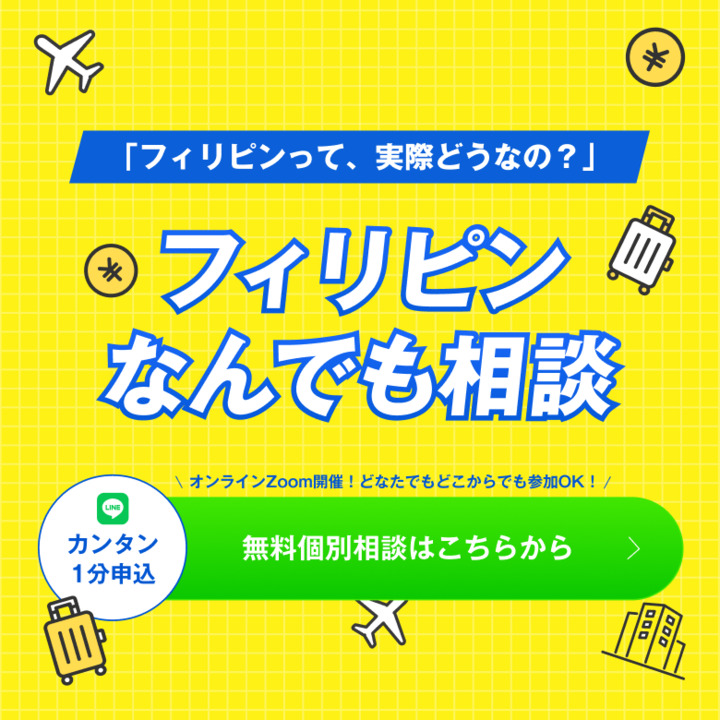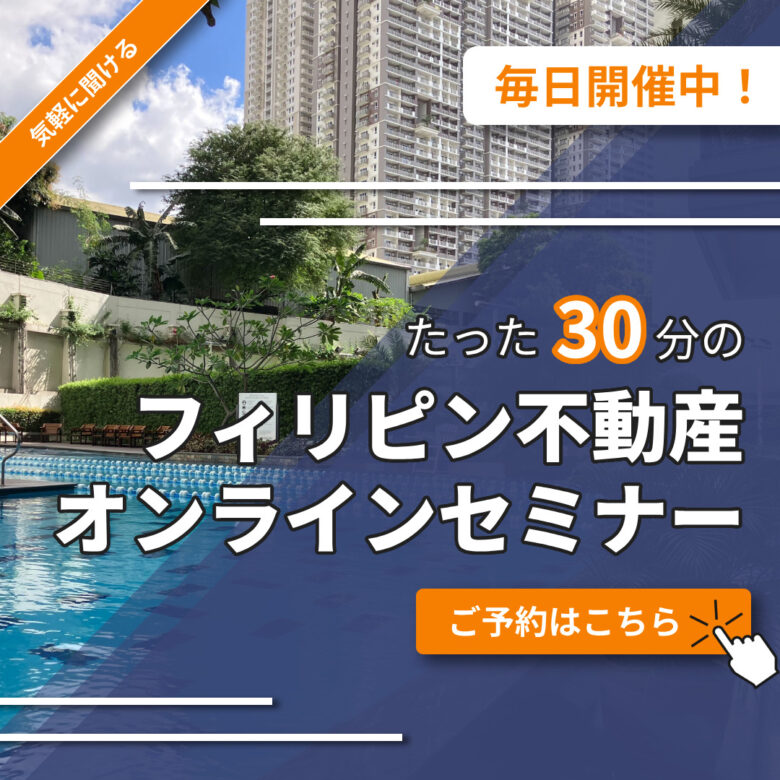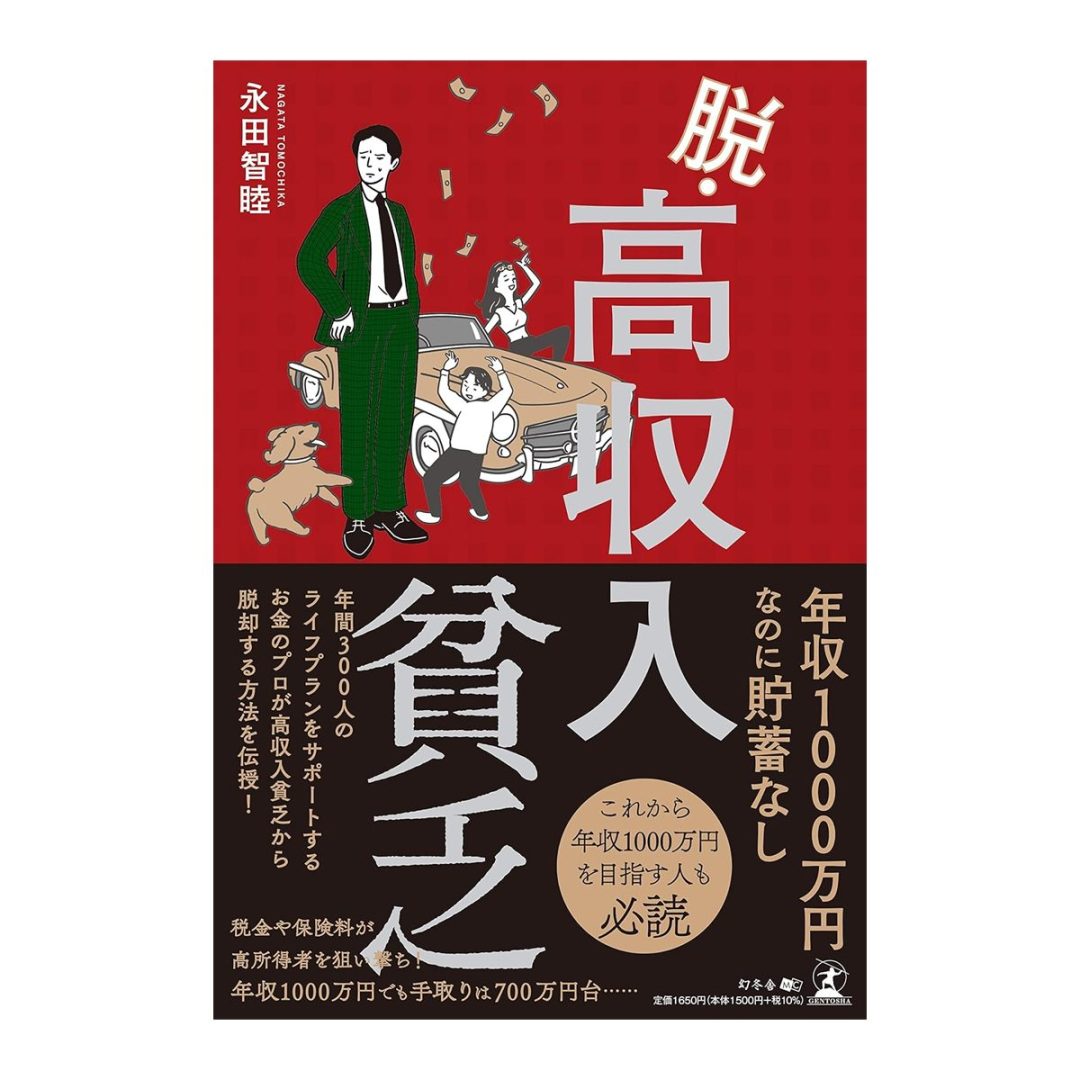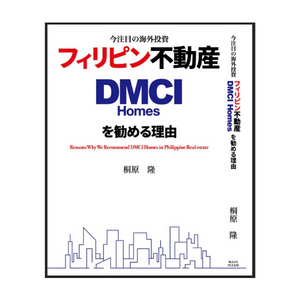近年、日本人の海外移住が過去最高を記録しています。この現象は、グローバル化の進展、多様な働き方の普及、そして国内外の経済状況の変化など、複数の要因が複雑に絡み合って生じています。かつて海外移住といえば、特定の職種や目的を持った人に限られるものでしたが、現在ではより多くの人々が視野に入れる選択肢となりつつあります。
このガイドでは、2025年における日本人の海外移住の最新動向を深掘りし、その背景にある社会経済的な要因を解説します。また、実際に海外移住を検討している方々に向けて、準備段階から移住先の選定、さらには現地での生活に至るまで、知っておくべき重要な情報を網羅的に提供します。あなたの「海外で暮らしたい」という夢を現実のものにするための、具体的なステップと役立つヒントをぜひ見つけてください。
目次
海外移住の現状と統計|過去最高を記録した海外永住者数

外務省の「海外在留邦人数調査統計」によると、2023年10月1日時点で海外に永住している日本人(永住者)の数は57万4,727人と過去最高を記録しました 。前年から約1万7,700人増加(+3.2%)しており、1989年の統計開始以来永住者数は20年連続で増加しています(※コロナ禍の影響で一時的な減少があった在留邦人総数も、永住者に限れば増加基調が続いています)。長期滞在者(3カ月以上の一時滞在者)と永住者を合わせた海外在留邦人総数は129万3,565人で、日本の人口減少問題の一因としても注目されています 。ただしコロナ禍の影響で2020~2021年は一時的に減少し、2019年に記録した約141万人の過去最多からやや減少しています 。それでも日本人の海外移住は長期的には増加傾向にあり、海外で生活拠点を築く人が着実に増えています。
海外移住が増加している理由

近年、日本人の海外移住が加速しています。一昔前までは一部の限られた人々が選択する道であった海外移住は、今やより多くの日本人にとって現実的な選択肢となりつつあります。
日本経済への不安
日本人の海外移住者増加の最大の要因は、日本経済の将来に対する不安です。特に若い世代を中心に、「このまま日本にいて大丈夫か?」という危機感が広がっています。
-
少子高齢化の進行:生産年齢人口の減少と社会保障費の増大により、将来の経済負担が増える懸念があります。
-
実質賃金の停滞:日本の平均賃金は過去30年間ほぼ横ばいで、先進国の中でも伸び悩んでいます 。他国(米英独仏など)が数十%賃金上昇している中、日本だけが停滞しており、働き続けても豊かさを実感しにくい状況です 。
-
社会保障制度への不安:年金制度の持続可能性に対する不信感が広がっています。少子高齢化により現在の給付水準を維持できるのか不透明で、「自分が将来十分な年金を受け取れるのか」という心配を抱く人も多いです。
-
経済成長の鈍化:日本の経済成長率や国際競争力の低下も指摘されています。GDP規模では世界3位を維持するものの、1990年からの伸び率は他国に大きく遅れ 、一人当たりGDPもG7中下位という現実があります。
こうした悲観的な見通しから、将来世代の日本人ほど将来への期待値が低くなっています。日本財団の「18歳意識調査」でも「自分の国の将来が良くなる」と答えた日本の若者はわずか15%で主要国中最下位であり、中国では96%が「良くなる」と回答しているなど顕著な差があります。つまり、多くの若者にとって「日本に留まっても明るい未来が描けない」という状況が、海外に活路を求める動機になっているのです。
リモートワークの普及
もう一つの大きな要因が、IT技術の進歩とコロナ禍を契機としたリモートワークの急速な普及です。場所にとらわれない働き方が現実味を帯び、日本国内の企業に所属しながら海外で生活したり、逆に海外の企業と契約してリモートで働いたりすることが容易になりました。例えばアメリカでは企業の85%が何らかのリモートワーク制度を導入しているとの統計もあり 、仕事はオフィスに通うものという常識が覆りつつあります。リモートワークの浸透により、「日本に住む必要がないなら一度海外で暮らしてみよう」と考える人や、地方より海外で働く方が魅力的だと感じる人も増えています。地理的制約がなくなったことで、優秀な人材の獲得競争がグローバルに激化しており、日本人もその中で新たなチャレンジを志向するようになりました。
海外移住のメリット
海外へ生活拠点を移すことには、不安要素だけでなく様々なメリットも存在します。主なメリットを経済面・生活面・リスク分散の観点から整理します。
経済的メリット
-
高い給与水準:先進国を中心に、日本よりも給与相場が高い国は少なくありません。特にITエンジニアや専門職の場合、海外では日本の倍近い年収が提示されることもあり、能力に見合った収入アップが期待できます。
-
生活費の最適化:移住先によっては物価が日本より大幅に安く、同じ収入でもより豊かな生活が可能です。例えば東南アジア諸国では日本の半分以下の生活費で暮らせるケースもあり 、年金や貯蓄で悠々自適に暮らすことも夢ではありません。
-
海外赴任手当:日本企業から駐在員として派遣される場合、現地での住宅補助や物価手当、子女教育手当など充実したサポートが受けられることがあります。赴任期間中に貯蓄を増やせるメリットもあります。
-
税制の違い:国によっては所得税率が低かったり、外国人向けの税優遇制度がある場合があります(※ただし税制は国ごとに異なり、移住前に専門家への確認が必要です)。適切に対策すれば、合法的な節税や資産運用の幅も広がります。
生活環境の改善
-
気候を選べる:寒暖差が苦手な人は常夏の国へ、四季が恋しい人は温帯の国へ、というように、自分に合った気候の土地で暮らせます。慢性的な寒さ暑さから解放され、健康状態が改善することも期待できます。
-
ワークライフバランス:欧米諸国を中心に、有給休暇の取得率が高かったり残業の少ない労働文化が根付いている国があります。そうした国では**「仕事のための人生」ではなく「人生のための仕事」**という価値観が強く、余暇を充実させやすい環境です。
-
多様な文化体験:海外で暮らすことで異文化に触れ、価値観や視野が広がります。多民族社会では多様性を学び、人種や宗教の違いを超えて協働するスキルも身につきます。異文化での生活経験自体が大きな財産と言えるでしょう。
-
語学力の向上:現地で生活する中で語学を実践的に習得できます。英語圏なら英語力向上はもちろん、その他の国でも現地語に触れることでバイリンガル・マルチリンガルになるチャンスです。語学力はその後のキャリアや人間関係にも大きなプラスになります。
リスク分散(リスク回避)
-
自然災害リスクの回避:日本は地震や台風など自然災害が多い国です。比較的災害の少ない国や地域に移住すれば、常に災害への備えや不安に追われることなく暮らせます。例えば地震活動の少ない国や内陸部の地域では、日本より安心して生活できるでしょう。
-
政治的リスクの分散:日本は政治的に安定した国ですが、それでも将来何が起こるかは分かりません。複数の国に拠点を持つことで、一国の政治・社会状況に人生を左右されにくくなります。政情の安定した国に移り住むことで、日本国内の政変や制度変更の影響を直接受けずに済む安心感があります。
-
経済リスクの分散:資産運用や収入源を日本国外にも確保することで、為替変動や日本経済低迷の影響を緩和できます。たとえば収入を外貨で得ることで円安の局面でも購買力を維持できる、といったメリットがあります。
-
教育機会の拡大:お子さんがいる場合、海外移住により国際的な教育環境を提供できます。現地校やインターナショナルスクールで多文化共生を学び、バイリンガルに育てることが可能です。将来グローバルに活躍できる人材に育てたいと考える家庭にとって、海外で子育てすること自体が大きな投資と言えます。
海外移住先を選ぶポイント

数ある候補国の中から自分に合った移住先を選ぶ際には、以下のポイントを総合的に検討すると良いでしょう。
基本的な生活環境
-
治安の良さ:毎日の生活の安心感に直結する要素です。外務省の海外安全情報や各国の犯罪発生率データなどを参考に、安心して暮らせる国・地域か確認しましょう。夜間外出の安全性や日本人に対する犯罪事例なども調べておくと安心です。
-
物価水準:ご自身の予算で無理なく生活できる国かどうかは重要です。家賃や食費、交通費など主要な生活費がどの程度か、事前に把握しましょう。都市部か地方かでも大きく異なるため、具体的な地域レベルでの物価調査がおすすめです。
-
気候の適合性:一年中暑い、または寒い、雨季と乾季がある、など気候は国によって様々です。暑さ寒さの耐性や健康面の相性も考慮しましょう。長期間住むとなると気候ストレスは侮れないので、自分や家族が快適に過ごせる気候かどうか確認が必要です。
-
食文化:毎日の食事を美味しく楽しめるかも重要です。現地の食事が口に合うか、和食材は手に入るかなどをチェックしましょう。特にお子さんがいる場合、好き嫌いやアレルギーへの対応も考慮し、現地で代替できる食品があるか確認しておくと安心です。
制度面の確認
-
ビザの取得しやすさ:移住目的(就労、結婚、投資、退職後など)に応じたビザの種類と取得条件を調べましょう。必要な収入や資金、年齢要件、スポンサーの有無など、国ごとに条件が異なります。長期的に安定した在留資格を得られるかも重要なポイントです。
-
医療制度:現地の医療水準や医療費負担について把握しましょう。公的医療保険に加入できるか、民間保険が必要か、日本語対応の病院はあるかなども確認します。特に高齢の方や持病がある方は、緊急時の医療体制が信頼できる国かどうかは移住の死活問題です。
-
教育制度:お子さん連れの場合、現地校に通うのかインターナショナルスクールにするのか、教育言語やカリキュラムはどうするかを検討します。日本人が多い地域では日本人学校や補習校がある場合もあります。また高校・大学進学時に帰国する可能性も見据えて教育プランを練りましょう。
-
税制:所得税や住民税の税率、消費税(付加価値税)の有無、不動産取得税など、その国で課される主な税金を確認します。二重課税防止条約の有無や、日本に資産が残る場合の日本側の課税関係も念頭に置きましょう。国によっては税率が高く手取りが減る可能性もあるため、収支シミュレーションをおすすめします。
海外移住の準備手順

海外移住は思い立ってすぐに実現できるものではありません。ビザや資金、言語や各種手続きなど事前に整えるべきことが多岐にわたります。以下では、移住の中長期的な準備と移住直前の準備に分けて主な手順を解説します。
中長期的な準備(移住の1~2年前から)
-
語学学習:移住先の公用語、もしくは共通言語としての英語の習得は最優先事項です。日常会話レベルはもちろん、就労や行政手続きに支障がないレベルが望ましいです。独学だけでなく語学学校やオンラインレッスンの活用、アウトプットの機会を増やすなど計画的に学習しましょう。現地の友人を作って会話する、言語交換をするなど実践も効果的です。
-
文化・慣習の理解:移住先の文化や宗教、マナー、法律などについて事前に学んでおきます。本やインターネット、YouTubeなどを活用し、その国のタブーや生活習慣、日本との違いを把握しましょう。可能であれば実際に移住した日本人のコミュニティ(SNSグループやブログなど)に参加し、生の声を集めると具体的なイメージが掴めます。
-
資金準備:移住には当初まとまった資金が必要です。一般的に以下の費用を見積もっておきましょう。渡航費、当面の滞在費、住居のデポジット(敷金)、ビザ申請料、引越し荷物輸送代など。先進国移住なら約150万円、発展途上国でも50万円程度は最低ラインとされます。
大きな出費として車の購入(必要な国の場合)や子どもの教育費なども考慮し、無理のない予算計画を立ててください。
移住直前の準備(移住の3~6ヶ月前)
-
ビザ取得:移住の目的に応じた長期ビザの申請・取得を行います。主要なビザの種類には以下のようなものがあります:
-
就労ビザ:現地企業への就職や日本企業からの駐在により取得(スポンサーとなる雇用主が必要)。
-
投資ビザ:現地で起業したり一定額以上の投資を行うことで取得。
-
リタイアメントビザ:一定年齢(多くは50歳以上)かつ一定の資産・収入がある退職者向けの長期滞在ビザ。
-
家族帯同ビザ:配偶者が現地人または就労者の場合、その扶養家族としての在留資格。
-
各ビザの要件(必要書類・手続き・審査期間など)を確認し、余裕を持って準備しましょう。ビザによっては日本国内の大使館・領事館でのみ申請可能なものもあるので注意が必要です。
-
パスポートの確認・更新:パスポートの有効期限を必ずチェックします。多くの国では入国時にパスポート残存期間が6カ月以上必要とされています。例えば有効期限が1年を切っているなら、出国前に更新手続きをして新しいパスポートを受け取っておきましょう。合わせてビザシール貼付の余白ページも十分あるか確認します。
-
各種証明書の準備:海外での手続きに必要となる日本の公的書類を取得しておきます。具体的には以下のようなものです:
-
戸籍謄本・戸籍抄本(家族関係や婚姻状況の証明に使用)
-
住民票(住所や世帯の証明。海外転出時には除票になるため事前取得)
-
所得証明書(市町村役場で発行。過去の収入証明として)
-
卒業証明書(学歴の証明。最終学歴校で発行)
-
健康診断書(ビザ申請で要求される国もあり。その場合指定フォーマットや提携病院が指定されることも)
-
これら日本の書類は英語翻訳とアポスティーユ認証が必要な場合があります。翻訳は公的な翻訳証明付きが求められることもあるため、早めに専門業者に依頼するか大使館指定の方法で用意しましょう。アポスティーユ(Apostille)とは、海外で日本の公文書を有効に使うための外務省による証明で、各種証明書を外務省領事局または法務局で認証してもらう手続きです。ビザ申請要件を確認し、必要に応じて取得してください。
税金と年金の手続き

海外移住に際し、日本での税金や年金に関する手続きを適切に行っておくことも重要です。うっかり手続きを怠ると、余計な税金を払い続けたり将来の年金受給に支障が出たりする可能性があります。以下に主要なポイントをまとめます。
海外転出届の提出
日本を出国して1年以上海外に居住する場合、住民票を管轄する市区町村役場に「海外転出届」を提出する必要があります。この手続きをすることで、以下の義務が免除・停止されます。
-
国民年金保険料の支払い義務:住民票を抜くと日本国内の国民年金第1号被保険者ではなくなるため、年金保険料の納付義務がなくなります 。
-
国民健康保険料の支払い義務:同様に国民健康保険も脱退となり、保険料支払いが不要になります (海外では日本の健康保険は使えません)。
-
住民税の支払い義務:毎年1月1日に日本に住民票がなければ、その年度の住民税は課税されません 。したがって前年の12月末までに転出届を出していれば、翌年度以降の住民税は発生しなくなります。
海外転出届の提出は原則として出国の2週間前から可能です。手続き後は住民票が「除票」となり日本に住所がない状態になります。これらの手続きを行わずに海外移住してしまうと、非居住者なのに日本の住民税や年金・健康保険料を払い続けることになりかねません ので、忘れずに済ませましょう。
所得税の取り扱い(居住者・非居住者)
海外移住後の日本の所得税は、税法上あなたが**「非居住者」になるか「居住者のまま」かで扱いが異なります** 。
-
日本非居住者となる場合(住民票を抜き、日本に生活実体がなくなった場合など):日本の税法上「非居住者」と判定されると、日本国内源泉所得(日本国内から得た所得)のみが日本で課税対象となります 。海外で得た所得(現地収入や海外資産からの所得)は日本では課税されません。例えば日本に残した不動産収入や、日本の企業から受け取る給与などは引き続き日本で課税されますが、それ以外(現地就労の給与や現地投資の利益など)は日本の所得税はかからなくなります 。非居住者には所得区分に応じて源泉徴収のみで課税完了とするものや確定申告が必要なものがありますが、いずれにせよ課税対象は限定的です(日本国外源泉所得は非課税)。
-
日本の居住者のまま海外に住む場合(例:海外赴任中でも家族が日本に住み続けている場合など):税法上「居住者」と見なされる場合、海外移住後も全世界所得が日本で課税対象となります 。つまり現地で得た収入も含め、日本に確定申告して所得税を納める必要があります。その場合、住民税も引き続き課税されます 。もっとも、二重課税を防ぐため日本と移住先の租税条約に基づき外国税額控除が受けられることが多いです 。例えばアメリカに納税した所得に関して、日本でも同じ所得に課税された場合は、その分を差し引く形で調整できます。ただ手続きは煩雑になるため、居住者・非居住者どちらに該当するか含め専門家への相談をおすすめします。
※「居住者」「非居住者」の判定は滞在日数や生活の本拠がどこにあるかなど総合的に判断されます。一時的な海外滞在では非居住者と認められない場合もありますので注意してください。
国民年金の取り扱い
海外転出届を提出して日本を非居住者となった場合、日本の国民年金は強制加入ではなくなります。しかし希望すれば任意加入制度によって引き続き国民年金に加入し保険料を納めることが可能です 。この任意加入は20歳以上60歳未満の日本国籍保持者が対象で、海外在住期間中も日本の年金制度に継続加入できる仕組みです 。
-
任意加入のメリット:将来受け取る年金額を減らさないためには、可能なら加入を継続することが望ましいです。年金は加入期間が10年以上ないと受給資格自体が得られませんが、海外転出中でも任意加入で期間を満たすことができます。また加入期間が長いほど老後にもらえる年金額も増えるため、余裕があれば払っておく価値はあります。保険料の納付は日本の預貯金口座から口座振替で継続可能です。
-
任意加入の手続き:海外転出前に管轄の年金事務所で手続きを行うか、出国後に日本年金機構へ郵送で届け出て加入することができます 。住民票を抜いた後は「第1号被保険者」から「任意加入被保険者」という扱いに変更されます。
-
年金の受給:加入期間が10年以上あれば、日本を含む海外どこに住んでいても将来老齢年金を受け取ることができます 。受給開始年齢(原則65歳)になれば、日本の銀行口座への振込や海外送金により年金が支払われます。海外在住者が年金を受給する場合、年に一度「現況届(生存証明)」を提出する必要があります 。これは誕生月ごとに日本年金機構から書類が送られてくるので、必要事項を記入し返送する形です。これを怠ると支給が止まるので注意しましょう。また受給開始時期・額は日本国内居住者と同じです。
納税管理人の選任
海外移住後に日本国内で確定申告や税金納付が必要となる場合、納税管理人を税務署に届け出る必要があります。納税管理人とは、日本において納税や申告を代理で行う責任者のことで、通常は日本在住の親族や知人、または税理士等に依頼します。
納税管理人が必要となるケースの例
-
日本に不動産を所有し賃貸収入などがある場合(非居住者でも日本の所得税申告が必要)
-
日本の企業から役員報酬や給与を受け続けている場合(源泉徴収されても年末調整や確定申告が発生する可能性あり)
-
日本株の配当や投資信託の分配金などがある場合(非居住者になると証券会社から強制的に売却させられる商品もありますが、一部収入は課税対象となり得ます)
海外転出後は市役所等からの郵便物転送が基本できなくなるため、税に関する郵便も含め納税管理人に送られることになります。納税管理人の届出は出国前に所轄税務署で行うのが一般的ですが、出国後でも可能です。信頼できる人に依頼し、万一日本で納める税金が発生した際に対応してもらえるよう手配しておきましょう。
当社では各種サポートやセミナーなど随時行っています。LINEにてお気軽にお問い合わせください。

金融機関の手続き

海外移住は金融面でもいくつか注意が必要です。日本の銀行や証券口座、クレジットカード等は利用者が非居住者になると利用制限がかかる場合があります。また現地での送金や新規口座開設も必要になります。
日本の金融機関の利用制限
日本の多くの金融機関では、「国外居住」となった顧客に対し以下のような制限を設けています。
-
新規口座開設停止:非居住者となった時点で、新たに銀行口座や証券口座を開くことは通常できなくなります(マイナンバー制度の関係上も日本在住でないと開設困難)。
-
投資商品の売買停止:証券会社によっては、非居住者になると株式・投資信託の売買ができなくなるケースがあります。既存の持ち高は売却を求められたり、配当受取のみ可能で取引不可となるなどの措置があります。
-
クレジットカードの更新拒否:カード会社によりますが、カード会員規約で日本在住を要件としている場合、更新時に住所が海外だと新カードを発行してもらえないことがあります。実際に海外在住を理由にカード契約解除となる例もあります。
-
住宅ローン等の一括返済要求:銀行によっては、住宅ローン借入者が海外転出すると期限の利益を喪失し繰上返済を求められることがあります。これは債権回収上のリスク管理による措置ですが、場合によっては事前相談で対応してもらえることもあるので、ローン利用者は出国前に金融機関へ確認が必要です。
こうした制限があるため、出国前に日本の金融資産の整理をしておくのがおすすめです。例えば使っていない銀行口座は解約する、主要な証券会社では非居住者でも保有継続できるか確認する、カードは有効期限を延ばしておく等の対応を取りましょう。海外在住中も利用したいサービスがある場合、非居住者でも利用可能な他社サービスに乗り換えることも検討してください。
海外送金の準備
海外で生活するには、日本から資金を送金したり引き出したりする手段を確保する必要があります。以下のような方法があります:
-
オンライン海外送金サービスの活用:近年はWiseやWestern Union、SBIレミットなど手数料の安いオンライン送金サービスが普及しています。日本の銀行から海外の自分口座へ直接安価に送金できるサービスを使えば両替手数料も抑えられ便利です。
-
外貨建て口座の開設:日本の銀行でも外貨預金口座を持っておけば有利なレートの時に外貨に替えておき、必要に応じて国外送金することが可能です。また現地通貨建ての預金商品を日本で用意できる場合、為替変動リスク分散になります。
-
国際的なデビットカードの利用:例えばWiseのマルチカレンシー口座+デビットカードなど、海外ATMで現地通貨を引き出せるカードを準備すると良いでしょう。為替手数料が安く、現金調達に重宝します。クレジットカードも海外ATMでキャッシングできますが利息がかかるため、デビットカードの方が有利です。
-
現地での銀行口座開設:現地に到着したら早めにローカル銀行口座を開設しましょう。給与振込や家賃支払い、公共料金引落などで必要になります。国によっては開設に住所証明や渡航ビザが必要なので、渡航直後は困難な場合もあります。その際は上記のデビットカード等でしのぎつつ、必要書類が揃い次第口座開設に臨みます。
保険の見直し
海外移住に伴い、これまで加入していた保険をどうするかも検討が必要です。また新たに必要となる保険もあります。
-
海外旅行保険・海外居住者保険:移住直後は現地の公的医療保険にすぐ加入できない場合があります。その際の医療費リスクに備えて、当初数カ月~1年程度は民間の海外旅行保険や海外在住者向け医療保険に加入しておくと安心です。日本に一時帰国する際の治療費をカバーする特約などもあります。クレジットカード付帯の旅行保険では長期移住はカバーできないため、市販の商品を検討しましょう。
-
生命保険の継続:日本の生命保険や医療保険に入っている場合、海外居住で給付対象外になるケースがあります。約款を確認し、海外在住中も保障が有効かどうか保険会社に問い合わせましょう。問題なければ契約を維持し、保険料の支払い方法を海外からでも可能な形(口座振替やクレジットカード払い)に変更します。もし加入中の保険が海外在住者に対応していない場合は、解約や一時払い込み停止、もしくは海外で新たに保険加入することも検討します。
-
連絡先や受取人の変更:生命保険等の受取人情報に変更がある場合(結婚・離婚など)や、連絡先住所を海外に変える場合は速やかに保険会社に届け出ます。海外住所だと郵便が届かないケースもあるため、日本の実家など代理受取先を登録することもできます。
移住後の生活立ち上げ
渡航して新天地に降り立ったら、早速やるべき手続きや生活基盤作りが待っています。最初の数ヶ月は何かと忙しいですが、以下のポイントを押さえてスムーズに新生活を軌道に乗せましょう。
入国直後の手続き
-
在留届の提出:海外に3カ月以上滞在する日本人は、現地の日本大使館・総領事館に「在留届」を提出することが義務付けられています。用紙提出やオンライン(ORRネット)で登録できます。これは滞在先情報を登録し、邦人保護(災害・事件時の安否確認等)のために重要です。
-
現地銀行口座の開設:可能な限り早めに現地の銀行口座を作りましょう。居住証明(住所の記載された公共料金請求書等)やパスポート、就労証明などが必要になる場合が多いです。口座ができれば給与の受取や家賃支払い、クレジットカード作成など金融面の利便性が飛躍的に向上します。
-
携帯電話・通信の契約:現地SIMカードを購入し、通信プランを契約します。プリペイドでも構いませんが、長期滞在なら月額プランの方が割安でしょう。日本との連絡はLINEやSkypeなどインターネット通話を使うと安上がりです。住所登録が済んだら固定インターネット回線やWi-Fi環境も整備しましょう。
-
住居の確保:住まい探しは現地入り直後の最重要タスクです。赴任の場合は会社が手配してくれることもありますが、そうでない場合、最初はホテルやサービスアパートメントを拠点に内見を重ねて部屋を決めます。契約時には保証金や前家賃が必要になり、契約書は現地語の場合も多いので慎重に。入居後は水道・電気・ガスの開設手続きも忘れずに行います。
社会保険制度への加入
現地での社会保障制度にもなるべく早く加入しましょう。
-
公的医療保険への加入:移住先によって制度は異なりますが、何らかの公的医療保険または医療サービスにアクセスできる仕組みがあります。就労者であれば会社経由で医療保険に加入するケース、退職者なら自費で国民健康保険的なものに加入申請するケースなど様々です。加入しないと医療費が全額自己負担になり大変なので、早急に手続きを。
-
労働保険(失業保険等)の確認:現地で就職した場合、失業保険や労災保険などに自動加入となるか確認しましょう。万一解雇された際の失業手当の条件や期間について把握しておくと安心です。自営業・フリーランスの場合はこれら無関係ですが、代わりに自分で積み立てや民間保険で備えることも検討が必要です。
-
年金制度:現地に公的年金がある場合、基本的には就労に伴い強制加入となることが多いです。掛金率や将来の受給資格(受給開始年齢や加入年数要件)を調べ、日本の年金との損益を比較しましょう。国によっては日本との間に社会保障協定が結ばれており、年金加入期間を通算できたり二重払いを防止できる場合があります。
-
税務当局への登録:現地で納税者になるための手続きも確認します。税番号の取得や確定申告の方法など、働き始めたら会社任せにせず自分でも基本を理解しておくと良いでしょう。
コミュニティとの関係構築
-
現地日本人会への参加:多くの国や都市には在住日本人が組織する日本人会やクラブがあります。イベントや交流会、情報共有の場として有益です。困ったときに助け合える仲間作りにもなりますので、積極的に顔を出してみましょう。
-
ローカルコミュニティとの交流:日本人ばかりと付き合うのではなく、ぜひ現地の人々との関係も築いてください。言語の練習にもなりますし、その国に溶け込むには地元の友人を作るのが一番です。近所付き合いや職場の交流、趣味のサークルに参加するなどして、人脈を広げましょう。
-
子供の教育環境の確保:お子さんがいる場合、学校や保育園への入学・入園手続きを現地ルールに沿って進めます。日本人学校やインターナショナルスクールの場合はウェイティングリストがあることも。現地校に入れる場合でも補習校で日本の勉強を継続するか検討しましょう。同年代の現地の子との交流も大切です。
-
医療機関の確認と登録:かかりつけ医や緊急時に駆け込む病院を決めておくことも重要です。周辺のクリニックや大病院の場所、救急連絡先などを把握し、保険証やIDを持って一度受診登録を済ませておくと安心です。持病がある場合は専門医を探して紹介状を持参するとスムーズでしょう。
海外移住の注意点とリスク

海外で新生活を始めるにあたっては、良いことばかりではなく様々な困難やリスクもあります。あらかじめ覚悟し、対策を講じておくことで失敗や後悔を減らすことができます。
文化的適応の課題
-
言語の壁:言いたいことが伝わらない、相手の言うことがわからないストレスは想像以上に大きいです。日常生活での些細なやりとりから役所での手続きまで、言語の違いは常につきまとう壁になります。慣れるまでは疲労感を覚えるでしょう。
-
価値観や習慣の違い:日本では当たり前だったことが通用しない、人々の考え方が自分と全く違う、といった場面に直面します。時間感覚のズレ(約束の時間に平気で遅れて来る等)や仕事の進め方の違い、宗教上のタブーなど、最初は戸惑うことも多いです。その積み重ねがストレスになる場合もあります。
-
孤独感や疎外感:異国の地で少数派として暮らすことは、時に孤独との戦いになります。言葉や文化が違う中で、自分だけが周囲に溶け込めていないように感じることもあるでしょう。家族で移住しても、本人や配偶者、子供がそれぞれ孤独を感じるタイミングがあります。日本にいる家族・友人との距離も物理的に離れるため、心細さを感じることもあります。
-
日本の家族や友人との距離感:特に高齢の親を残して移住する場合、親不孝ではないかと悩んだり、逆に緊急時にすぐ駆けつけられないもどかしさがあります。また、友人関係も徐々に疎遠になる可能性があり、日本に一時帰国しても話が合わないと感じることも出てくるでしょう。
経済的リスク
-
為替変動による生活費変化:現地通貨と円の為替レートが大きく動くと、日本からの仕送りや年金の価値が目減りしたり、逆に日本円で貯めた資金が現地通貨で増えたりします。為替次第で生活コストが変動するリスクは常につきまといます。
-
現地での就職の困難:思ったような仕事に就けず、貯金を切り崩す期間が長引くリスクもあります。外国人として採用市場で苦戦したり、言語ハンデで希望職種につけないケースもあります。最悪の場合、予定より早く貯金が底をつき帰国を余儀なくされる可能性もゼロではありません。
-
予期せぬ医療費の発生:公的保険に入っていても、カバーされない治療や海外ならではの高額な医療費が発生することがあります。日本で受けていた持病の治療が現地では保険適用外で高額になる、といったケースもあり得ます。また歯科や眼科など保険外治療費も想定しておきましょう。
-
日本への緊急帰国費用:日本の家族の不幸や病気などで急遽帰国しなければならない事態も起こりえます。その際の航空券代や滞在費など、まとまった出費が必要です。距離によっては往復で数十万円単位になることもあり、緊急予備資金が無いと対応できません。
法的・制度的リスク
-
ビザ更新・延長の不許可:現地で気に入って長く住みたくても、ビザ延長が認められなければ退去せざるを得ません。法律や政策の変更でそれまで可能だった滞在ができなくなるリスクもあります。特に移民政策が変わりやすい国では注意が必要です。
-
税制の変更による負担増:移住先で大幅な増税や社会保険料引き上げが行われる可能性もあります。せっかく移住したのに税負担が日本より重くなってしまった、という事態もゼロではありません。これは予見しづらいリスクですが、常にアンテナを張り対応策を考えておくことが重要です。
-
現地法律の理解不足によるトラブル:日本では合法でも現地では違法ということがあります(例:ある国では電子タバコ所持が違法、他の国では薬の持ち込み制限など)。法律知識が乏しいまま行動すると、知らずに法を犯してしまうリスクがあります。また契約社会では口約束が通用せず、契約書の読み違いで不利な状況に陥ることもありえます。
-
日本の社会保障制度からの離脱:海外転出届を出すことで日本の国民健康保険や年金の強制加入から外れます。任意加入しない限り年金受給資格を満たせなくなる恐れや、医療費全額負担に直面することになります。日本国内での社会保障を放棄することになるので、そのデメリットを十分理解した上で移住する必要があります。
海外移住ならフィリピンがおすすめ!その魅力とは?

数ある海外移住先の中でも、近年、コストパフォーマンスと利便性のバランスが取れた国として、日本人に密かに人気が高まっているのがフィリピンです。特に都市部に限ればインフラや医療も整備されており、初めての海外生活にもおすすめできる国のひとつと言えるでしょう。
フィリピンが海外移住に向いている理由
物価が安く、生活コストを抑えやすい
フィリピンの生活費は、日本の1/3〜1/2程度と言われています。例えば、マニラ郊外での1LDKの家賃相場は月2万〜5万円程度と手頃で、水道光熱費や交通費も格安です。食費も外食を含めて日本よりはるかに安く抑えられます。これにより、節約しつつも、外食や買い物、レジャーなどを十分に楽しめるため、経済的な負担を軽減しながら、日本よりも豊かな生活感を得やすい国です。
英語が公用語で言語の壁が低い
フィリピンは英語が事実上の公用語であり、行政手続き、教育、医療など、日常生活の多くの場面で英語が通じます。国民の英語力も高く、TOEIC平均スコアもアジア圏ではトップクラスです。そのため、日本人にとって英語の実践練習環境としても最適であり、語学力の向上を目指す方や、留学、子育て目的で海外移住を考えている方にとっても住みやすい国です。
日本との距離が近く、時差も小さい
日本からフィリピンの首都マニラまでは直行便で約4〜5時間と、比較的短時間でアクセスできます。さらに、時差もわずか1時間であるため、時差ボケに悩まされることが少なく、日本にいる家族や友人との連絡も取りやすいです。リモートワークで日本の企業と連携する場合でも、時差の調整が非常にしやすく、ビジネス面での利便性も高いと言えます。
日本人コミュニティ・日本食も充実
マニラやセブなどの主要都市には、日本人学校、日系企業、そして数多くの日本食レストランが存在します。これにより、初めての海外移住でも孤独感を感じにくく、いざという時のサポートも期待できます。日本の食材や製品も手に入りやすいため、日本食が恋しくなることも少ないでしょう。このような充実した日本人コミュニティは、安心して海外生活を送る上で非常に重要な要素となります。
リタイアメント先としての魅力(SRRVビザ)
フィリピンは、退職後の海外生活を考えている方にも非常に人気があります。特に注目すべきは「SRRV(特別居住退職者ビザ)」という制度です。これは35歳以上であれば取得可能で、預金や年金収入などの条件を満たせば、永住権のように長期滞在が可能です。温暖な気候、物価の安さ、そしてフレンドリーな国民性も相まって、退職後の豊かなセカンドライフを送るための理想的な場所として選ばれています。
まとめ

日本人の海外移住者数は過去最高を更新し、今後も増加が予想されます。その背景には前述したように日本経済への将来不安や働き方の変化(リモートワーク)などがあり、多くの人々がより良い暮らしやキャリアを求めて海外に目を向け始めています。
最初から完璧を求めず、まずは短期間の滞在から始めてみる。そして自分に合った国・地域を見つけ、段階的にステップアップしていくことをおすすめします。
フィリピンは「英語が使える」「物価が安い」「日本に近い」といった、海外移住における理想的な条件をバランス良く備えた国です。特に近年はリモートワーカーや若年層、リタイア世代の間でも注目度が高まり、長期滞在や移住者が急増しています。
まずは短期滞在や視察旅行から始めて、自分に合ったライフスタイルかどうかを確認してみるのも良いでしょう。
当社では海外不動産投資のためツアーや個別面談なども行っています。LINEにてお気軽にお問い合わせください。